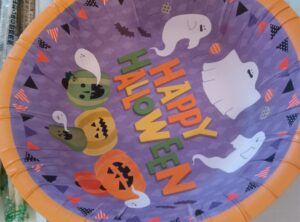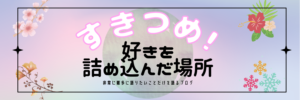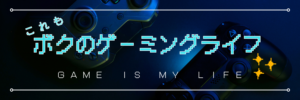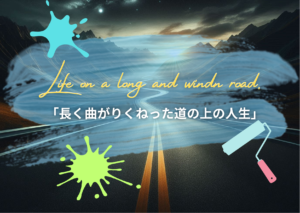Life on a long and winding road.「長く曲がりくねった道の上の人生」vol.10
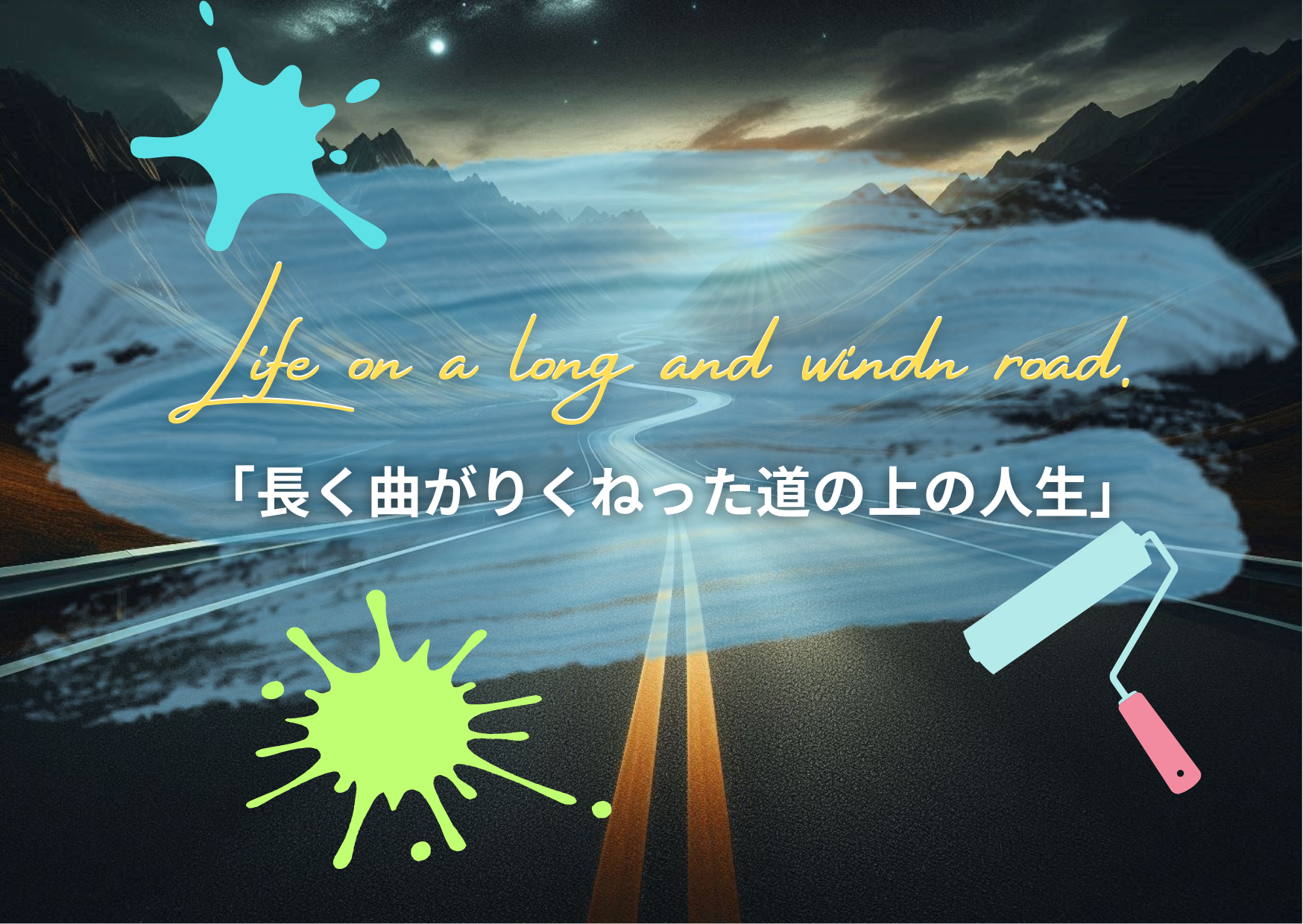
第18章:現実への失望
地域活動支援センターに通いながら、ハローワークで就職活動を開始しました。何度か面接を重ね、ある企業の役員面接まで進みましたが、残念ながら内定をいただくことができませんでした。と言うか障がい者枠にも関わらず、圧迫面接でした。その後、グループホームを移転し、少しずつ以前の自分を取り戻しつつあった頃、大学や専門学校で、他のメンバーの体験談を語る活動を始めました。その際、私が作成したPowerPoint資料や自分の経験談が評価され、ある専門学校の教授から「PSW1を目指してみませんか?」と温かい言葉をいただきました。
PSWか…。正直、大きな目標として掲げるほど、この仕事に強い情熱があるわけではありません。これまでの経験から、「人は一人では生きていけない」と感じると同時に、「人のサポートには限界がある」という現実も目の当たりにしてきました。例えば、「立ち直るきっかけさえ与えれば、あとは本人の努力次第」という考え方も一理あると思っています。
様々な経験を経た今では「努力では無く、本人だけの対処法に自身で気付き、実践を重ねる事で自分のモノにする事」かと思います。しかし、心のどこかでは、誰かの役に立ちたいという思いと、亡くなられた母のことが重なり合っているのかもしれません。
しかし、センター内で発生したトラブルをきっかけに、残念ながら退所することになりました。センター長からは、「残念ながら、こちらでお手伝い出来ることは何もないです」との言葉をいただき、「では本日をもって退所させて頂きます。これまでお世話になりました」と返答しました。
地域活動支援センターに通所中でもハローワークの障がい者枠に応募する際、履歴書や職務経歴書の作成、面接対策など、必要なサポートを受けることができず、すべて自己完結せざるを得ませんでした。
しかしながら率直に申し上げると、障がい者枠の求人に見られる給与や労働条件は、多くの場合、自立した生活を送るには厳しい現実だと感じています。例えば、ある企業の特例子会社では、週5日、1日8時間の勤務で、手取りが11万円から12万円程度という求人がありました。これでは、家賃や光熱費を支払った後、十分な生活を送るのは難しいでしょう。
企業は、法定雇用率2を満たすことだけでなく、障がいのある人たちが働きやすい環境を整え、自立した生活を送れるよう、より高い賃金や充実した福利厚生を提供すべきではないでしょうか。SNSで「昔よりは障害者に対する差別や偏見はなくなった」と発信する企業がありましたが、その主張には私がこれまで経験してきた現実との乖離が大きく、非常に安易な考えだと感じました。
目の前に立ちはだかるあまりにも大きな現実の壁。
この出来事がきっかけとなり、再び困難な時期を迎え、友人と酒に溺れるなど、精神的に追い詰められていきました。そんな中、以前お世話になった地域活動支援センターのPSWの方と連絡を取り、相談に乗ってもらううちに、少しずつ立ち直ることができました。そして、今度は就労移行支援事業所3を紹介していただきました。
今度は軽作業ではなく、レストランの運営スタッフとして、ホール、洗い場、仕込み、調理補助など、幅広い業務を担当しています。元シェフの方々が4人いらっしゃり、我流だった調理を基礎から教えていただいています。通勤は電車通勤。しかし、初日に施設長から「ここではあなたは障害者として扱いません」と言われ、戸惑いを隠せませんでした。
施設長の「ここではあなたは障害者として扱いません」という言葉は、私にとって、自分の能力を過小評価されているように感じられ、やる気を削ぐものでした。私は、他の従業員と同じように仕事に取り組みたいと考えており、特別扱いを求めているわけではありません。しかし、このような発言は、職場全体の雰囲気を悪くし、居心地の悪さを感じさせます。
その後いろいろな出来事があり職場は、人間関係の悪化やモラルの低下により、非常に働きにくい環境になっていました。この状況に強いストレスを感じ、私は再びパニック障害の症状が悪化し、電車に乗ることができなくなりました。心身ともに疲弊し、残念ながら短期間で職場を離れることになりました。
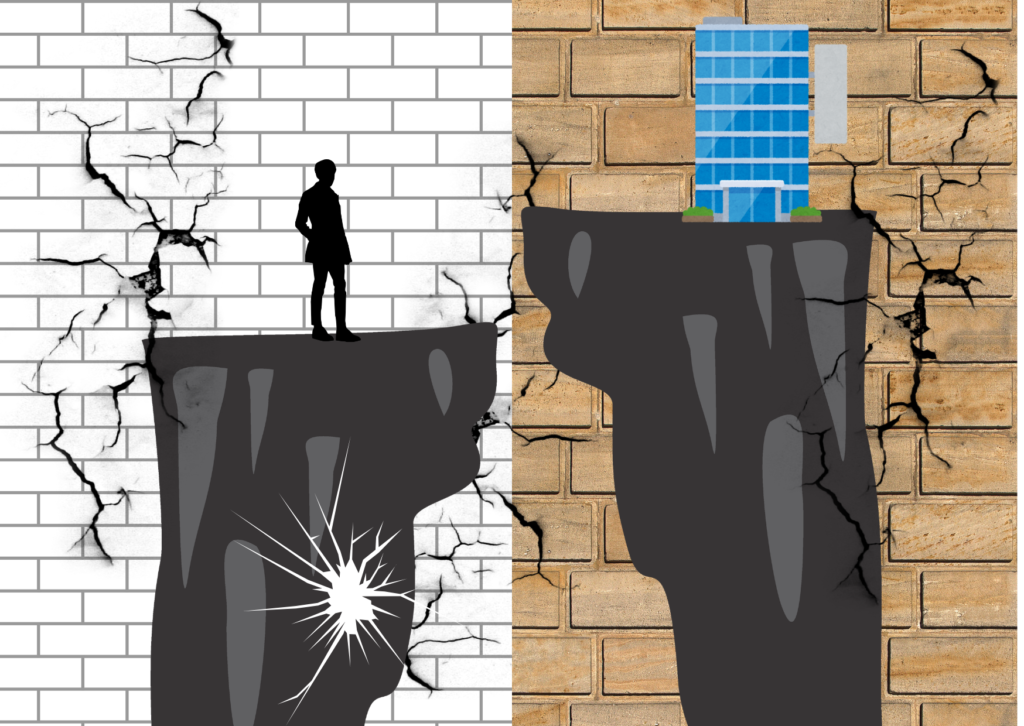
目の前の現実と就労移行支援事業所で学んだ事
1.障害者を取り巻く社会の課題
- 雇用における課題: 障害者雇用における賃金格差や、職場環境の整備不足など、障害者が働きやすい社会を実現するための課題が浮き彫りになっています。
- 社会の理解不足: 企業が障害者に対する理解を深めていないこと、差別や偏見が根強く残っていることなどが示されています。
- 支援体制の課題: 地域活動支援センターや就労移行支援事業所など、障害者の就労を支援する機関の体制や、支援内容の多様化が求められています。
2.個人の成長と葛藤
- 自己肯定感の変容: 障害を持つことへの悩みや、社会との関わり方など、自己肯定感が大きく揺れ動く様子が描かれています。
- 目標設定の難しさ: 将来の目標を定めることの難しさや、目標に向かって進む際の葛藤が表現されています。
- 人間関係の重要性: 周りの人との関わり方や、人間関係の良し悪しが、自身の精神状態に大きな影響を与えることがわかります。
3.具体的なエピソードから得られる教訓
- 障害者雇用における現実: 障害者雇用が法的に義務付けられているものの、現実には様々な課題が存在することがわかります。
- 職場環境の重要性: 働きやすい職場環境が、障害者の就労継続に大きく影響を与えることがわかります。
- 心のケアの必要性: 障害を持つ人だけでなく、誰もが心のケアを必要とする可能性があることが示されています。
4.まとめ
- 障害者を取り巻く社会には、まだまだ多くの課題が存在する。
- 障害者雇用は、単に法定雇用率を満たすだけでなく、働きやすい環境を整えることが重要である。
- 障害を持つ人は、周囲のサポートを受けながら、自分自身のペースで社会参加を目指していく必要がある。
- 障害者支援に関わる人たちは、それぞれの状況に合わせて、多様な支援を提供していく必要がある。
- 支援者は最低限のモラルを持ち合わせていないと利用者の体調悪化の引き金になりかねない
第19章:暗闇から光明を見出す
立て続けに起きた離職とパニック発作は、私を打ちのめし、自信を大きく失墜させました。絶望感の中で孤独に過ごした日々を送り、自問自答していました。
絶望感の中で、ある日一線を越えてしまい、ICUで目が覚めました。意識がもうろうとする中、まるで夢を見ているようでした。医師からは、胃洗浄が間に合わず、10日間意識不明の状態だったと告げられました。枕元のぬいぐるみが目に入りました。それは、当時の恋人が届けてくれたものでした。その後、別の病院に移り、保護室での拘束を経験しました。拘束具は、私を深淵へと引きずり込む鎖のように思えた。渾身の力で拘束具を引っ張ると、金属が軋むような音がするばかりで、びくともしなかった。それでも力を入れ続けていると、女性の悲鳴の後に男性スタッフが数名、保護室に飛んできて鎮静剤の注射をされました。「これで、やっと楽になれるのか」と思ったのもつかの間、「いや、私はまだ生きているんだ」という絶望的な現実が心に突き刺さった」
それから閉鎖病棟に移り、他の患者さんと話せる様になるまで回復してきました。親切にもテレホンカードを同室の方が貸して下さり、とりあえず当時の恋人に謝罪の連絡をしました。それから数週間後に退院する事になりました。
退院後、グループホームから一般のアパートに引っ越す事になり生活を一新しようと決意した。しかし、新たな住まいを探していた際、思わぬ出来事があった。福祉関係の不動産から紹介されたアパートが、実は事故物件だったのだ。なぜ、その物件を特に勧めてきたのか疑問に思った。入居前に告知義務があるはずなのに、何も知らされなかった。
この経験を通して、福祉に対して、社会に対して不信感を抱いた。それでも前を向いて生きていかなければならない。さてどうしようか?とりあえず、ここまでハイペースだった歩みを一旦ギアを落としてローペースにしよう。失った自信を取り戻そう。そして相談できる友人と繋がりたいと保健士さんに相談した結果、自立訓練施設4を勧められました。
前の就労移行支援事業所では、経験を積んだ上で調理師免許を取得したいと考えていました。こちらの自立訓練施設の母体が調理関係の事業所を展開していると伺い、再びその目標に向かって進んでみようという気持ちになりました。まだ先のことですが、少しだけ前向きな気持ちになれたことが嬉しかったです。
この施設では、利用者みんなで昼食を作ることがルールで、私も積極的に調理に参加していました。元々、料理が得意だったのもあり、我流だった包丁さばきや火加減等を一から学びました。調理担当の方から様々なレシピを教えていただき、料理の幅が広がりました。担当の方がお休みされる際は、カレーなど比較的簡単な料理の段取りを任せていただくこともありました。信頼して任せてもらえることに喜びを感じると同時に、責任の重大さからくる緊張感も、どこか心地よいと感じていました。
少しづつ環境に慣れて、施設長から声をかけられて調理の地域活動支援センターの見学。そして試用期間で入る事になりました。
しかし残念ながら、平穏な日々はまたしても崩れ去る事になります。

一人で悩みを抱えて自分自身を追い詰めてしまった経験で学んだこと
1.精神的な側面
- 心の病の深刻さ: 精神疾患は、本人のみならず周囲にも大きな影響を与える深刻な問題であることを認識できます。
- 回復の道のり: 精神疾患からの回復は、決して一筋縄ではいかない長期戦であること、そして周囲のサポートがいかに重要かを知ることができます。
- 再発のリスク: 一度回復しても、再発のリスクは常に存在することを理解できます。
- 心の柔軟性: 困難な状況でも、心の柔軟性を持つことで、新たな目標を見つけ、一歩を踏み出すことができることを示唆しています。
2.社会的な側面
- 福祉制度の問題点: 福祉制度には、まだ改善すべき点が多く存在することを示唆しています。
- 人とのつながりの大切さ: 友人や周囲の人とのつながりは、困難な状況を乗り越える上で大きな支えとなることを教えてくれます。
- 社会への貢献: 社会に貢献したいという思いが、生きる喜びや目標につながることを示唆しています。
3.成長と変化
- 自己肯定感の回復: 困難な経験を乗り越えることで、自己肯定感を回復し、新たな自分を見つけることができることを示唆しています。
- スキルアップ: 困難な状況を乗り越える中で、新たなスキルを習得し、成長することができることを示唆しています。
- 目標に向かって進むこと: 目標に向かって努力することで、達成感や充実感を得ることができることを示唆しています。
4.まとめ
- 自分自身と向き合う大切さ: 困難な状況に直面した時、自分自身と向き合い、何が大切なのかを考えることが重要です。
- 周囲の人とのつながり: 周囲の人とのつながりが、心の支えとなり、生きていく上で大きな力となることを認識しましょう。
- 変化を恐れない: 新しい環境に飛び込むことを恐れずに、変化を受け入れていくことが大切です。
- 目標に向かって努力すること: 目標を持つことは、生きる上で大きなモチベーションとなります。
- 人生の無常さ: 人生は常に変化し、予測不可能な出来事が起こることを教えてくれます。
- 希望を持つことの大切さ: どんな状況でも、希望を持つことが大切であることを教えてくれます。
…to be continued
脚注
- 精神保健福祉士は、精神障害のある方とそのご家族に対して、様々な支援を行う専門家です。具体的には、
相談援助: 精神障害に関する悩みや困りごとについて、本人や家族から相談を受け、解決に向けた支援を行います。
社会資源の活用: 医療機関、福祉施設、地域社会など、必要な資源を繋ぎ、生活をサポートします。
権利擁護: 精神障害のある方の権利を守り、社会参加を促進します。
教育・啓発: 精神障害に対する理解を深めるための教育や啓発活動を行います。
など、多岐にわたる活動を行っています。
↩︎ - 法定雇用率とは、企業や行政機関などが、従業員に占める障害者の割合を一定以上にすることを法律で義務付けたものです。つまり、企業は法律で定められた割合以上の障害者を雇用しなければならないということです。
障害者の雇用機会の拡大: 障害者の方々が、より多くの企業で働く機会を得られるようにするためです。
多様な人材の活用: 障害者の方々の多様な能力や経験を企業が活かすことで、企業全体の活性化につながることが期待されています。
共生社会の実現: 障害者と健常者が共に働き、共に生きる社会の実現を目指しています。
法定雇用率の目的
障害者に対する社会全体の意識改革を促す
障害者の自立を支援する
企業の多様性と包容性を高める
法定雇用率の計算方法
法定雇用率は、企業の従業員数に対して、雇用すべき障害者の数を割合で表したものです。計算方法は法律で定められており、障害者手帳の種類や雇用形態によって異なります。
法定雇用率を満たさない場合
法定雇用率を満たさない企業に対しては、指導や勧告が行われます。それでも改善が見られない場合は、行政処分を受ける可能性もあります。
法定雇用率に関する注意点
法定雇用率は最低基準: 法定雇用率はあくまでも最低基準であり、企業は法定雇用率を上回る努力が求められます。
障害の種類や程度: 障害の種類や程度によって、必要な支援や配慮は異なります。
雇用後の支援: 障害者を雇用した後も、継続的な支援や育成が必要です。
現在の法定雇用率
法定雇用率は、定期的に見直されており、近年では引き上げの動きがあります。最新の法定雇用率については、厚生労働省のホームページなどで確認することができます。
障害者雇用に関する支援
障害者雇用を推進するため、国や地方自治体、民間企業など様々な主体が、様々な支援を行っています。
ハローワーク: 障害者の方の就職支援
障害者職業能力開発施設: 職業訓練
助成金制度: 障害者の雇用や職場環境整備に対する支援
↩︎ - 就労移行支援事業所は、障害のある方が、一般企業への就職を目指し、必要な知識やスキルを習得するための場所です。就職活動のサポートも行っており、障害のある方が安心して働くことができるよう、様々な支援を提供しています。
就労移行支援事業所でできること
職業訓練: オフィスワーク、接客業など、様々な職業に必要なスキルを習得するための訓練を行います。
就職活動のサポート: 企業探し、面接対策、履歴書作成のサポートなど、就職活動に必要な一連のサポートを行います。
職場体験: 実際の職場を体験することで、仕事のイメージを掴み、自分に合った仕事を見つけることができます。
相談支援: 就職に関する悩みや不安など、一人ひとりに合わせた相談に応じます。
職場定着支援: 就職後も、職場での悩みや困難に対応し、定着をサポートします。
↩︎ - 自立訓練施設は、障害のある方が、日常生活を送る上で必要な能力を身につけ、より自立した生活を送れるようにするための支援を行う場所です。 ↩︎