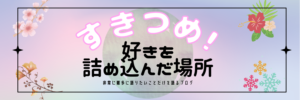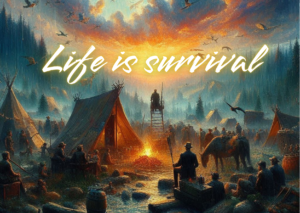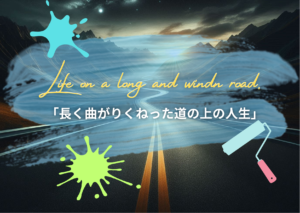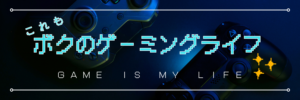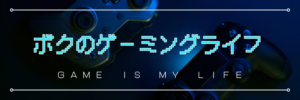Life is survival〜人生はサバイバル〜
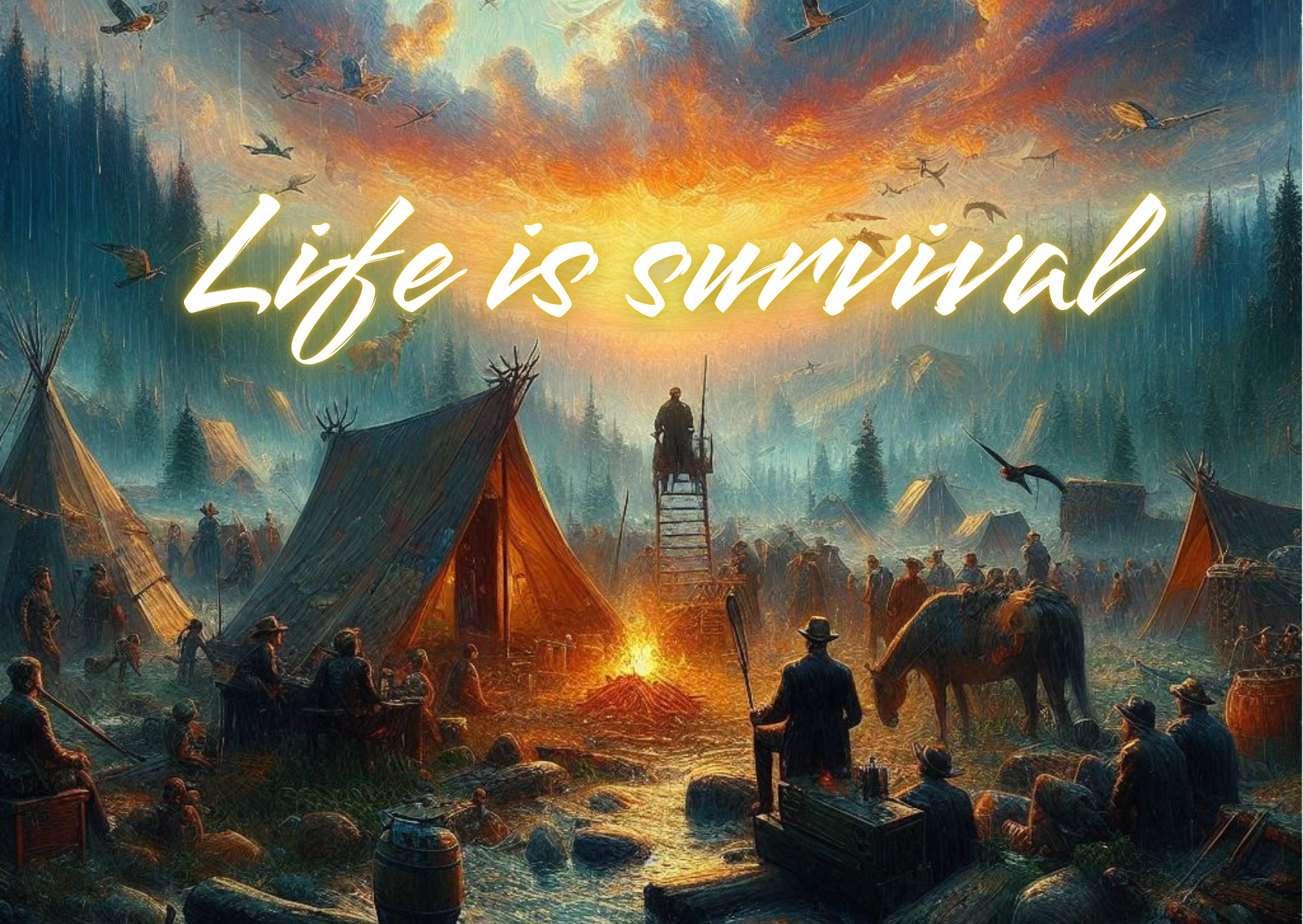
第13章:今のクリニックで判明した本当の病名
デイケアから作業所の件は以前の記事で書いたため、ここでは割愛します。
ここでは、今のクリニックで本当の病名が判明した経緯を書いてみようと思います。
人生で初めて心療内科を受診したのは29歳の時でした。その時の診断名は自律神経失調症。その後、別のクリニックでは統合失調症、その次は双極性障害、さらにパニック障害、気分変調症と、病院やクリニックを転院するたびに病名が変わっていきました。自分としては、この点がどうしても納得できませんでした。そこで、いくつか可能性として自分の中で仮説を立てていました。
① 多くの精神疾患は、症状が良い時と悪い時を繰り返す、いわゆる病気の波があります。受診時の状態によって診断が変わる可能性があるのではないか?
② 仮に複数の精神疾患を合併している場合、どの症状が強く出ているかによって診断名が変わることがあるのではないか?
③精神医学の診断はDSM-51に基づいての診断基準に基づいています。しかし、医師によっては症状の解釈や重症度の判断に、経験や知識、患者とのコミュニケーション不足がある場合や、診察時間が短いと正確な体調を判断できないのではないだろうか?
外傷ならば見た目での判断は比較的容易でしょう。しかし、精神疾患や体の内部の病気、難病など内部障害2においては特に診察での丁寧な問診が重要であると私は考えています。今までの病院やクリニックでは、長くても5分程度で、最短だと30秒という診察時間でした。そのクリニックでは、院長の有名な現象らしく、他の患者さんから「エレベーター診察」と呼ばれていました。しかし、カルテにはしっかりと書き込んであるのです。
これでは、余程注意深く診察しない限り、本当の状態を見抜けるはずもありません。因みに当時の体調は想像するまでもなく最悪でした。
今のクリニックでの診察時間は30分です。主治医の話では、これでも足りないくらいとのことです。そもそも、人を診るのに5分で分かるはずがありません。
そして、医師とのコミュニケーションが円滑に連携していないと、信頼関係も築けるはずがありません。今までの医師の中には、こちらをほとんど見ずにパソコンを眺めているだけで終わる人もいました。これでは、患者も本音を話せる環境ではありません。
29歳に発症してから今のクリニックに辿り着いたのが6年ほど前。こちらのクリニックで初めて「成人期ADHD」であることが分かり、丁寧な問診を重ね、こちらのクリニックで初めて「成人期ADHD」である事が分かり、丁寧な問診と過去の話等を重ねて、WAIS3(ウェスクラー成人知能検査)とAQ検査4を受けて確定診断となりました。
長かった。本当に長く感じました。診断がつくまでに20年もの時間を費やしたのです。
当時、服薬をしても体調が改善することはありませんでした。医療従事者、保健師、福祉関係者の方々も、私の話す症状を誰一人として信じてくれませんでした。
それでも、ようやく自分の根本にあるのがADHDだと判明しました。病気を免罪符にしたいのではなく、自分の本当の精神疾患を見つけてもらえたことが、純粋に嬉しかったのです。
最初からこちらのクリニックに通院できていれば、あるいは今とは違った人生だったかもしれません。しかし残念ながら、過去に戻ることは決してできません。失われた時間も戻ることはありません。様々な思いが去来しますが、今まで通院した精神科や心療内科の医師たちの診察は、誤診というよりは、当時の医療水準や知識では限界があったのだろうと、自分自身を納得させるようにしています。
それまでは何度か入院し、ICUや保護室に入ったことさえありましたが、こちらに転院してからは以前と比べて体調が格段に安定し、一度も入院していません。
私が経験した精神科・心療内科の見分け方(あくまで私個人の考えです)
- 診察時間を十分に確保し、患者の話を丁寧に傾聴してくれる
- 症状や処方された薬の説明に加え、起こりうる副作用についてもきちんと説明してくれる
- 常に最新の医療情報を把握しており、新しい薬にも精通している
- 信頼関係を築け、円滑なコミュニケーションが取れ、安心して本音を話せる環境がある
- 患者の障害特性を理解し、それに合わせた話し方をしてくれる
こうして書き出してみると当たり前のことばかりですが、残念ながら多くの精神科・心療内科を転院した中で、これらの条件を満たすのは現在のクリニックの主治医だけでした。今の主治医は私には合っていますが、それが全ての人に当てはまるとは限りません。なぜなら、薬に体質による相性があるように、医師との間にも相性があるからです。
第14章:そして現在は難病と格闘中
これまで私は、さまざまな困難に直面するたびに、その都度最適な解決策を模索し、実行することで成果を上げてきました。ところが、2015年6月、母の逝去に匹敵するほどの大きな壁が、私の前に突如として立ちはだかったのです。
その日、いつもなら問題ない運動量で激しい息切れ、倦怠感、胸痛に襲われました。現在も通院しているSAS(睡眠時無呼吸症候群)のクリニックで医師に相談したところ、すぐに胸部レントゲン撮影が行われ、「肺に判断しにくい影があります」とのこと。
これほどの自覚症状がある以上、何も異常がないはずがないと感じた私は、最悪の場合、肺がんやCOPD、あるいは別の疾患を疑っていました。ただし、自己診断に偏ることの危険性については、これまでの経験から学んでいたため、冷静に対処する必要があるとも感じていました。結果として、早急な精密検査が必要と判断され、後日、別の検査施設で全身CT検査を受けることになったのです。
検査結果のCD-ROMと封筒を受け取り、今度は大学病院へ。ここからが、終わりの見えない検査の日々の始まりでした。検体検査(採血)、生体検査、胸部レントゲン、CT、MRI、心エコー、心電図、腹部エコー、肺機能検査、6分間歩行検査、気管支鏡検査…。来る日も来る日も検査が続き、何のための検査なのかもわからないまま、自宅と大学病院を往復する日々でした。
そして、ついに確定診断が下された病名は「サルコイドーシス」。医療系の大学受験で基礎医学に少し触れた程度の知識しかなかった私にとって、聞いたこともない病名でした。調べた結果、それは原因不明で、いまだに治療法が確立されていない難病——指定難病84の一つであることが分かりました。
呼吸器内科の主治医の説明は淡々としていて、私には理解しづらく、何を質問すればいいのかさえ分かりませんでした。
「さて、どうしたものか。これまでの経験で何か活かせることはないだろうか」——そう自問自答しながら、まずは難病情報センターでの情報収集から始めました。原因不明で治療法が未確立であることは事前に調べていたため、年間の罹患率、主な症状、対処療法、検体検査におけるマーカーの基準値(上下限)、各検査項目の意味や、それが高値の場合に考えられる合併症などを詳しく調べました。
次に、自助グループの存在を確認しようと考え、SNSで同じ病気の方とつながれる可能性に期待し、いくつかのSNSに登録。自らもサルコイドーシスの闘病ブログを開設し、情報交換を試みました。同じ病気の方もブログを運営しているだろうと予想していたのです。なぜなら、年間の罹患率は約10万人に1人と希少で、周囲の理解を得るのが難しく、私自身も強い孤独感を抱えていたからです。
どのような病気でも、「自分だけがこの病気なのではないか」という思いは、やがて恐怖や不安に変わり、孤独感を深めてしまいます。精神疾患を併発する人も少なくないでしょう。人は一人では生きていけないのです。
自助グループはネット検索ですぐに見つかりました。「サルコイドーシス友の会」です。ホームページを念入りにチェックし、どのような活動を行っているか、医師の監修があるか、年会費はいくらか、情報誌の発行はされているかなどを確認しました。残念ながら、病気を悪用する団体も存在するため、慎重に調べた上で、入会の意思と現状を簡潔に記したメールを送信しました。こうして入会し、数カ月おきに届く会報誌で、サルコイドーシスに関する情報を継続的にアップデートしています。
医師に質問する際も、ある程度の予備知識と専門用語を身につけておく必要があると感じました。分からないことはその都度質問し、不安を少しでも解消するよう努めました。専門用語は事前に調べ、その理解が正しいかを医師に確認してもらうようにしました。
当時、私は調理師免許の取得を目指し、就労移行支援で実習を行っていましたが、肺の疾患のため、立ち仕事は諦めた方が良いと告げられました。夢を諦めるのは、これで二度目です。ならば、他の分野で自分の力を活かせる道を探すしかありません。この程度の苦難で諦めてなるものか。最後まで足掻き続けて生き抜いて見せる。病を抱えていても、人は誰しも幸せになる権利がある——そう自分に言い聞かせ、今はテレワークという形で懸命に働いています。
ある恩師からの言葉が、私の考え方を大きく変えてくれました。「今の体調でできることを考えて、実行した方がいい」。それまでの私は「体調が良くなったら…」「痛みがなくなったら…」と、前向きなようでいて実は後ろ向きだったのだと気づかされたのです。
難病は悪化することはあっても、治ることはありません。だからこそ、目指すのは「いかに安定させるか」。精神療法についても様々に調べ、実践を始めました。
特に胸部の慢性疼痛に対しては、鎮痛薬がほとんど効かないため、認知行動療法の一種であるストレス・コーピングが大いに役立っています。
参考までに自分が書いている闘病ブログです。
サルコイドーシスとの旅路〜日々の挑戦と小さな勝利〜
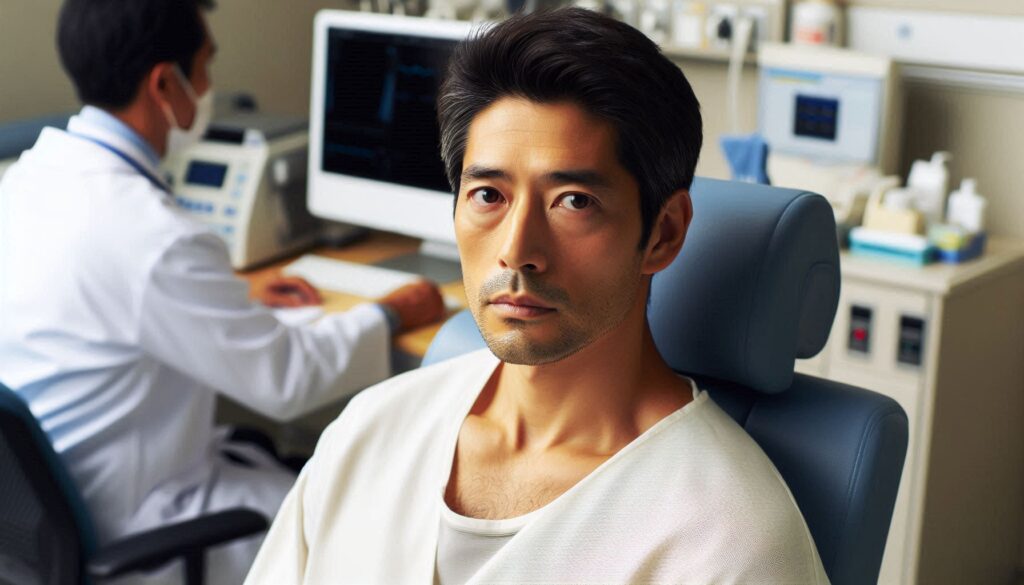
注釈
【重要】この情報は一般的な知識提供を目的としたものであり、医学的なアドバイスや診断、治療を目的としたものではありません。ご自身の健康状態や医療に関するご質問は、必ず医師やその他の資格のある医療従事者にご相談ください。この情報に基づいてご自身の判断で治療や対策を行うことは危険を伴う可能性があります。
- DSM-5(ディーエスエムファイブ)は、アメリカ精神医学会(American Psychiatric Association; APA)が発行している「精神障害の診断と統計マニュアル 第5版」(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition)の略称です。
DSM-5は、精神医学の専門家が診断を行うための重要なツールであり、一般の方が自己診断に用いるべきものではありません。精神的な問題や症状に悩んでいる場合は、専門の医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
↩︎ - 内部障害とは、外見からは分かりにくい、体の内部の機能に障害がある状態を指します。具体的には、心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、膀胱・直腸、小腸・大腸、免疫機能などに慢性的な機能不全が生じ、日常生活や社会生活に支障をきたす状態をいいます。
↩︎ - WAIS(ウェイス)とは、Wechsler Adult Intelligence Scale(ウェクスラー成人知能検査) の略称で、16歳から90歳11ヶ月までの成人を対象とした、世界的に広く使用されている個別式の知能検査です。
↩︎ - AQ検査(Autism-Spectrum Quotient:自閉症スペクトラム指数)とは、個人の自閉症スペクトラム(ASD)の傾向を数値化するための心理検査です。 ↩︎
AI bot Geminiより