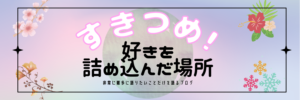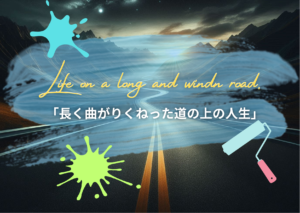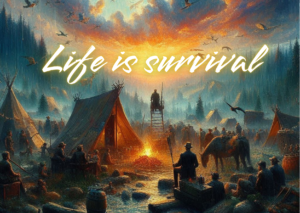物価高の時代を生き抜く処世術 vol.6 「暑熱順化」と熱中症対策のおさらいとアップデート
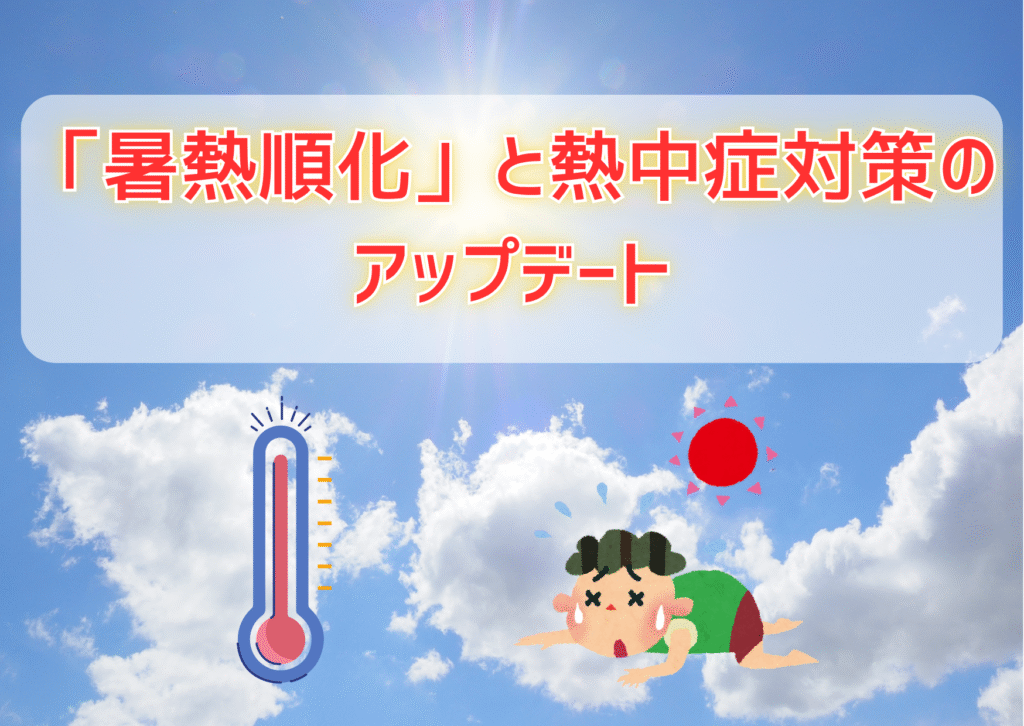
今年の異常な暑さ
今年は梅雨明け前から真夏日が続き、梅雨明け後は連日の猛暑日。この記事を書いている現在の最高気温は39℃に達し、まさに暑さのピークを迎えています。体温を超えるような気温の中、熱中症や夏バテに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
また、例年であれば騒がしく感じるセミの鳴き声が、今年はどこか少なく感じられます。このような現象について科学的な視点から検証しつつ、熱中症対策をより効果的にするための「暑熱順化」のアップデート方法について考えてみたいと思います。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。最後までお読みいただけたら嬉しく思います。
基本の熱中症対策🌞🥵
まずは基本の熱中症対策をおさらいしてみましょう。基本的な熱中症対策とは下記の通りです。
- 喉が渇く前にこまめな水分補給を心がけて実行する🥤
- 汗をかいた時や排泄時はスポーツドリンク等で塩分補給😅🥤
- 室内では適切な冷房の使用🍃
- 外出時は帽子·日傘を使用する👒☂️
- 歩く時はなるべく日陰を歩く様にする🚶♀️
- 3食はしっかり食べて暴飲暴食にならない生活を心がける🍚
- アルコール·カフェインは利尿作用があるので水分補給には適さない☕
- 寝不足の時は熱中症のリスクが上がるので無理はしない😪
- 基礎疾患がある方は健常者よりもリスクが高くなるので熱中症になりやすい😷
下記からはそれぞれの熱中症対策の解説をしていきます(-⊡ω⊡)ゞクイッ
1. こまめな水分補給🥤
- 喉が渇く前にこまめに水を飲むのが基本。喉が渇いたと感じる時はすでに軽い脱水症状になっている可能性があります。またマスク着用時は喉の渇きに気付きにくくなります。
- 汗をかいたときは塩分(ナトリウム)も同時に摂取(経口補水液やスポーツドリンクなど)。特に多量に汗をかいた場合や水分補給で尿の回数が多い時はナトリウムが体外に排出されるために水だけだと低ナトリウム血症1となります。
- カフェインやアルコールは利尿作用があるため控えめにしましょう。
2. 暑さを避ける🌞
- 外出はなるべく朝夕の涼しい時間帯に。買い物は朝夕に済ませると体への負担が少なくなります。
- 外では帽子や日傘を活用し、日陰を選んで歩く。
- 屋内ではエアコンや扇風機を適切に使い、室温を28℃以下に保つ。
3. 服装の工夫👕
- 通気性がよく、吸汗・速乾性のある素材(綿やリネン、機能性インナー)を選ぶ。
- 薄手でゆったりした服装が理想。
4. 睡眠と食事をしっかり取る😴🍋🍙
- 睡眠不足や栄養不足は体温調節機能を弱め、熱中症のリスクを高める。
- ビタミンB1やクエン酸を含む食品(豚肉、レモン、梅干しなど)を積極的に。
5. 暑熱順化を行う😎🌞
- 徐々に暑さに慣れる体作り(毎日30分の軽い運動や入浴など)を数週間かけて行う。
そもそも暑熱順化とは🤔❓
「暑熱順化(しょねつじゅんか)」とは、体が暑さに慣れていく生理的な適応プロセスのことを指します。
🔍 暑熱順化の概要
暑熱順化が進むことで、熱中症にかかりにくくなり、暑さに強い体になります。
✅ 暑熱順化によって起こる主な変化
暑熱順化の前🥵🌡🌞
- 発汗:遅く少なくなる(非効率的)
- 汗の成分:ナトリウム(塩分)が多く含まれる
- 体温調節:体温が上がりやすい
- 心拍数:高くなりやすい
- 血液量:体全体を循環する量が少ない
汗をかく事が遅く少なると体内の熱が逃げにくくなります。その結果として熱中症になりやすくなります。人間の体は体の機能を一定に保つための機能があります。これを恒常性維持(ホメオタシス)2と呼称します。
暑熱順化の後😎🌡🌞
- 発汗:早く多くなる(効率的)
- 汗の成分:ナトリウムの排出が抑えられる
- 体温調節 :体温が安定しやすい
- 心拍数 : 安定する
- 血液量 : 増加し循環が良くなる
🕒 順化にかかる期間
3日〜1週間程度で体は徐々に暑さに慣れはじめます。
完全な暑熱順化には1〜2週間程度かかると言われています。
☀️ 暑熱順化の方法(安全に行うには)
- 軽い運動から始める(ウォーキング、軽いジョギングなど)
- 涼しい時間帯に行う(朝や夕方など)
- こまめな水分補給(汗をかいても脱水にならないように)
- 無理をしない(体調が悪くなったら中止)
🧓 特に注意が必要な人
高齢者
持病がある人(心疾患、肺疾患、糖尿病など)
屋内で長期間過ごすことが多い人
これらの人は暑熱順化が進みにくいため、熱中症対策がより重要です。
📝 まとめ
暑熱順化とは、体が暑さに適応して熱中症になりにくくなるための変化。運動や日常生活で少しずつ暑さに慣れることが大切です。
😎自作スポーツドリンクのレシピ🥤
ここまで書いていて気がつきましたが、最近は特に自動販売機の飲み物の値段が上がっていますよね。ペットボトル飲料は通常の自販機で購入すると180円。何本も買うとなかなかの出費になるので、今回は私がよく作っている自家製スポーツドリンクのレシピをご紹介しようと思います。
梅干しはナトリウム(塩分)を含み、熱中症対策や夏場の電解質補給に適しています。以下は、梅干しを使った手作りスポーツドリンクのレシピです。梅干しの値段はピンキリですが安いもので構いません。
🍹梅干しスポーツドリンク(1人分・約500ml)
材料
- 梅干し(塩分8〜10%)……1個
- はちみつ(または砂糖)……小さじ1~2(甘さはお好みで調整)
- レモン汁(または酢)……小さじ1
- 塩……ひとつまみ(※梅干しの塩分に応じて調整)
- 水……500ml
作り方
- 梅干しの種を取り除き、果肉を細かく刻む(またはスプーンで潰す)。
- ボトルやピッチャーに水を入れ、梅干し・はちみつ・レモン汁・塩を加える。
- よく混ぜて冷蔵庫で冷やす。
※すぐ飲む場合は氷を加えてもOK。
⛱ポイント
- 甘さ控えめがお好きな方は、はちみつなしでもOKです。
- クエン酸(レモン汁)+ナトリウム(梅干し)+水分で、バランスよく補給できます。
- 運動後や発汗後におすすめ。冷やすと飲みやすくなります。
さらにアレンジしたい場合は
りんご酢(レモン汁の代用)でまろやかな酸味に
炭酸水で割ればリフレッシュドリンクに
🍹梅干しスポーツドリンク(砂糖で安価版/1人分)
はちみつの価格は依然として高騰が続いています。また、乳児のいるご家庭では、ボツリヌス菌による乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、はちみつを与えることができません。
そのため、今回ははちみつの代わりに砂糖を使用したレシピをご紹介します。
材料
- 梅干し(1個)
- 砂糖(上白糖 or グラニュー糖)……小さじ1~2
- レモン汁(ポッカレモンなどでもOK)……小さじ1
- 塩……ひとつまみ(梅干しの塩分によっては省略可)
- 水……500ml
作り方
- 梅干しの種を取って果肉を潰す(または刻む)。
- ボトルに水を入れて、砂糖・レモン汁・潰した梅干しを加える。
- よく混ぜて冷やせば完成。
✅さらに節約したいときの代替案:
| 高価な材料 | 安価な代替 |
|---|---|
| はちみつ | 砂糖(上白糖)またはみりん(小さじ1) |
| レモン汁 | 酢(穀物酢や米酢)少量(小さじ1弱) |
※ 酢を使うと独特の風味が出るので、少しずつ加えて好みで調整してください。
🌟甘さ控えめ・糖質制限したい方へ:
- 砂糖なしでも、梅干しとレモン(または酢)だけで塩気と酸味は十分効いていて、さっぱり飲めます。
- 梅干しの塩分が高ければ、塩は入れずにOK。
手作りの梅干しスポーツドリンクの保存期間は、以下の条件によって変わります。
🧊【冷蔵保存の場合】
- 保存期間の目安:冷蔵庫で約2日以内に飲み切るのが安全です。
理由:
- 梅干し自体には抗菌効果がありますが、
- 水を加えることで雑菌が増えやすくなる
- 砂糖やレモン汁なども菌の栄養源になりやすい
- 特に夏場は菌の繁殖が早いため、作り置きは短めに。
✅安全に保存するコツ:
- 清潔なふた付き容器やペットボトルを使用(煮沸かアルコール消毒が理想)
- 作ったらすぐ冷蔵庫へ
- 飲むときは直接口をつけない(コップに注ぐ)
- 作り置きしたものは1日目での消費がおすすめ
🧃【冷凍保存は不可?】
味は劣化し、梅干しの果肉や塩分が分離しやすいため、冷凍には不向きです。梅干しを使った自家製スポーツドリンク用の粉末は、手間はかかりますが保存が利き、持ち運びも便利です。以下に、家庭でできる「梅干し風味の粉末ドリンクの作り方」をご紹介します。
🧂自家製 梅干しスポーツドリンク粉末の作り方
【材料】※約5〜6回分
- 梅干し……2〜3個(塩分10%前後のもの)
- 砂糖(または粉末ステビア等)……大さじ4(お好みで調整)
- 塩……小さじ1
- クエン酸(※食品グレード、なくてもOK)……小さじ1/4(レモン風味に)
【作り方】
① 梅干しの下ごしらえ
- 種を取り除き、果肉をペースト状に潰す。
- 耐熱皿やクッキングシートの上に薄く広げる。
② 乾燥させる(以下のいずれか)
- 天日干し:
2~3日程度、風通しの良い場所で干す(直射日光OK)
→ 乾燥剤と一緒に保管する - オーブンやトースター:
100℃前後で1〜2時間(焦げないよう注意) - 電子レンジ:
キッチンペーパーで包み、500Wで30秒ずつ様子を見ながら数回加熱し、パリパリになるまで乾燥させる。
③ 粉末にする
乾燥させた梅肉をミルサー、すり鉢、包丁で細かくし、粉末化する。
④ 調合する
- 梅粉末・砂糖・塩・クエン酸(ある場合)をよく混ぜる。
【保存方法】
- 密閉容器(小瓶やチャック付き袋など)に入れ、冷暗所または冷蔵庫で保管。
- 保存期間: 約1か月程度(湿気に注意)
【使い方】
- 水500mlに小さじ1~2(約5g)を溶かすだけ!
→ 梅風味の即席スポーツドリンクに。
✅補足
- クエン酸がない場合は「レモン汁」をその都度加えてもOK。
- 粉末ステビアやラカントに変えれば糖質オフ対応も可能です。
ポッカレモンや酢すら無いときでも、梅干しだけで作るスポーツドリンク風のレシピは可能です。梅干しにはすでに塩分・酸味(クエン酸)・ミネラルが含まれているため、最低限の機能性は維持できます。
今年の夏は猛暑日が観測史上で過去最多を更新
東京では観測史上、過去最多となる猛暑日となりました。この記事を書いている現在でも熱中症警戒アラートが出ています。何故、夏の気温が上昇しているのか科学的に推察検証してみたいと思います。
1. 地球温暖化(グローバルな背景)
- 世界的に二酸化炭素などの温室効果ガスが増加 → 地表全体の平均気温が上昇。
- 日本周辺でも長期的に夏の平均気温が上がり、猛暑日そのものが発生しやすい土台になっています。
- 気象庁の解析でも、過去数十年で東京の平均気温は明確に上昇傾向にあります。
2. ヒートアイランド現象(都市特有の要因)
- アスファルトや建物のコンクリートが昼間に熱を吸収 → 夜間も放出して気温が下がりにくい。
- 車やエアコンなどの排熱が都市に熱をため込む。
- 緑地や水辺の減少により、自然の冷却作用が弱まっている。
→ 結果として、都市部は周辺より数度高い気温になることが多い。
3. その他の気象的要因
- 今年の夏は太平洋高気圧が強く、関東に安定して暑い空気が流れ込んだ。
- フェーン現象や大気の流れの停滞によって、熱がこもりやすくなった。
4.総括
🌍 地球温暖化で猛暑が起こりやすい基盤ができ、
🏙️ 東京のヒートアイランドでさらに気温が押し上げられた
という二重構造が、観測史上最多の猛暑日につながったと考えるのが妥当です。
【注意事項】※この記事は、筆者の個人的な見解と経験に基づいた考察に加え、OpenAIのAIツール「ChatGPT」による情報提供をもとに構成しています。
AIが提供する内容は参考情報であり、最新の気象情報や公式見解を保証するものではありません。
医療・気象・経済などの重要な判断をされる際は、必ず専門機関や公的情報をご確認ください。
脚注
- 低ナトリウム血症とは
血液中の ナトリウム濃度が正常より低くなる状態 のことです。
正常値:おおよそ 135〜145 mEq/L
低ナトリウム血症:135 mEq/L 未満
ナトリウムは体内で「水分のバランス」や「神経・筋肉の働き」を保つために欠かせない電解質なので、濃度が下がると全身に影響が出ます。
主な原因
水を摂りすぎた場合
発汗や排泄で塩分が減っているのに、水だけを大量に飲む → 血液が「薄まる」
ナトリウムの喪失
大量の汗
下痢や嘔吐
利尿薬の使用
体の水分調整異常
心不全、腎不全、肝硬変などで体に水がたまり、相対的にナトリウム濃度が下がる
症状(軽度〜重度)
軽度(130前後):頭痛、吐き気、倦怠感、注意力低下
中等度(120台):めまい、混乱、歩行のふらつき
重度(120未満):けいれん、意識障害、最悪の場合は生命の危険
なぜ問題なのか
ナトリウム濃度が下がると、細胞の外より内に水が移動してしまい、脳細胞が膨張 → 脳浮腫 が起こり、症状が急激に悪化します。
対策
軽度〜予防:
→ 発汗・下痢・嘔吐時には水だけでなく「ナトリウムを含む飲料(スポーツドリンクや経口補水液)」を摂る
重度(医療が必要な場合):
→ 点滴で慎重にナトリウムを補正 ↩︎ - ホメオスタシスとは
外部環境が変化しても、体内の状態を一定に保とうとする仕組みのこと。
体温、血糖値、血圧、血中pH などを安定させる働きがあります。
体温調節とホメオスタシス
体温が上がったとき、体は「熱を逃がす方向」に働きます。
これは自律神経とホルモンを介したフィードバック制御によって行われています。
体温上昇 → 視床下部の体温中枢が感知 → 以下の反応を引き起こす:
発汗:汗が蒸発する際に熱を奪う(気化熱)
皮膚血管拡張:血流を皮膚に集めて熱放散を促進
呼吸の増加(浅く速い呼吸):呼気で熱を放散
排泄:尿や便でも熱や代謝産物を外に出す(体温調節への影響は汗に比べ小さい)
逆に寒いときは
皮膚血管収縮
震え(筋肉運動で発熱)
代謝亢進
→ 体温を逃がさない方向に調整されます ↩︎